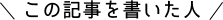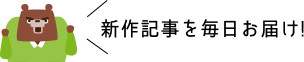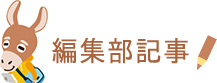選ぶ時間にこそ価値がある。 レザーブランド「GIVING LIFE」オーナーインタビュー
山手駅で下車して1分も歩かないうちにそのアトリエの印象的な青いドアがみえてくる。
鉢植えのブルーベリーが小さな白い花を付けていて、ドアのクリアガラスには「GIVING LIFE」の文字。
その字体からはいかにも実直な職人気質が感じられた。
アトリエに入ると手掛けている革製品の展示スペースがあり、その奥によく整理された道具箱のような作業場が広がっている。
明るい白壁に落ち着いた色の無垢のフローリング、ちょっとしたカフェのように耳ざわりのいい音楽が控えめに流れる。レザーブランド「GIVING LIFE」のオーナーはここでモノづくりをしている。
「GIVING LIFE」のコンセプトはGIFT。
たとえば誰かにプレゼントをするとき。その人のことを想いながら革や糸の色を選ぶ時間にこそ価値があるのではないか?
そんな時間を提供できるモノづくりを目指していこうというスタンスなのだ。
だからこそセレクトオーダーにしても細かい部分まで自由度高く受けている。なによりその価値を大事にしているオーナーのモノづくりには「受注したものをつくる」以上に「喜ばれるGIFTとして贈れるものをつくる」という気概が感じられる。
お客さんが選ぶ革の色、糸の色、そしてワンポイントの刺繍
丁度取材中にアトリエにお客さんが入ってきて、展示されている革製品を一つ選んだ。近くに住んでいる様子でお店のことは前から気になっていたという。記念日のプレゼントを探して、なにかイメージに合うものはないかなと来店したとのことだ。
革や糸の色が決まると、お客さんから革に入れるメッセージをヒアリングする。少し考えていたが「ではこれでお願いします」と、そのやりとりはとても雰囲気のあるものだった。ああ、まさにこの時間には価値がある。傍目でみていてとても納得感があった。
革へのメッセージや名入れを自由にオーダーできるし、なにより最近はじめたワンポイントの刺繍もいくつかの柄を選べるのが嬉しい。ギフトとしての親しみやすさもそうだが、刺繍を選ぶことで誰かのことを想う時間の質が変わっていくのではないだろうか。ぴっちりした革の上に遊び心を載せるとでもいえばいいのだろうか、メッセージを選ぶときとは少し違って、お客さんの「どうしよっかなー、じゃあこれで!」は、ほころんでいたように感じられた。
革の匂いには新しい季節の物語がある
何の匂いでしょう
これは
これは春の匂い
真新しい着地(きじ)の匂い
真新しい革の匂い
新しいものの
新しい匂い
匂いのなかに
希望も
夢も
幸福も
うっとりと
浮かんでくるようです
ごったがえす
人いきれのさなかで
だけどちょっぴり
気がかりです
心の支度は
どうでしょう
もうできましたか
黒田三郎「支度」
革を手に取っていると、この季節だからか個人的にはなんとなくランドセルを思い浮かべたりする。素材はいろいろとあるのだろうけど、ランドセルも日本人にとっては子供の頃に共通して贈られるGIFTだとは言えないだろうか。
だからなのか新しいことをはじめるとき、新しい環境に身を置くときの感覚は、革の匂いに少なからず紐づいているように感じられる。むしろそんな節目には新しい革製品がそばにあることがしっくりとくる気がするのだ。
まあでも案外それは自分の独りよがりではないのかもしれない。使いはじめてから心地よく経年変化していく色合いも含めて、おそらく革は新しい季節と相性がいいのだろう。
そしてプレゼントするまでの時間だけではなく、浮き沈みのある日常の中でちょっぴり「気がかり」に想い続けられる時間にも同様に価値があるように思える。そんな長い時間のなかで深まっていく繋がりを彩るために、革製品はささやかながらいい味を加えてくれるはずだ。そんな考えがアトリエ「GIVING LIFE」では浮かんでくる。
コーヒーをいれてもらい、オーナーのこれまでを聞かせてもらう
30歳を過ぎたばかりの「GIVING LIFE」のオーナーは10年前は会社に勤めて飛行機をつくっていたという。ある日、リーダーが子どもの運動会の日に出社していて「仕事ってそういうもんだよ」と平然と言ってたことを当時は受け入れられなかったそうだ。そして、自分の時間を管理できるようにならないといけないと思ったという。「若さもあったんだろうけど、人生を考えるきっかけになったよ」とオーナーは少しはにかんだ。
「もともと飛行機の専門学校に入ったのも、おそらく父親の工具箱に憧れていたんだと思う。その箱から道具を取り出して自転車の修理をしてくれる姿。自分も工具箱を持ちたいと考えるようになったんだ」そう振り返りながら、在りし日の感動を鮮やかに伝えてくれた。
そしてオーナーには、モノづくりのセンスのようなものが自分にはあるのでは?と感じることがあったという。そのセンスの定義を語ってくれたが、とても興味深いものだった。
『革製品もそうだけど一から十まで自分で加工するわけで、それは「一つ一つの選択の集合」といっても過言ではない。なのでモノづくりというのは「いっちゃえ!」と「…丁寧にいこう」を常に見極める感性が大事なんじゃないかな』
オーナーは会社勤めの頃からそのセンスにはある程度自信があったそうで、将来独立してモノづくりができないかを漠然と考えるようになったという。
そんな折、手に取った雑誌でレザーカービングに出会ったことが人生の転機になる。ヒゲを蓄えた職人の手で革に巧みに彫刻された絵や模様に心を奪われたのだ。そしてその熱情が冷めることはなかった。1年かけて仕事を辞めて大阪での暮らしを整理しきった日に、満を持してそのカービングを極めたヒゲの革職人の工房がある横浜までバイクを飛ばして門戸を叩く。
まさに猪突猛進。なんの事前連絡もなしに、雑誌をみて「きちゃいました!」と弟子入りを申し込む。しかしかなりロングスパンで助走をとって飛んだもののヒゲの革職人は「今ちょっと人は募集してなくて…」とさらっと断ってしまう。そしてとりあえずその職人がやっている革の教室に通う事になるという話が、波乱万丈すぎてものすごく惹きつけられた。
扉のわきにそのヒゲの革職人が革で作った「カツオノエボシ」が飾ってある。最近会った時にアトリエに置いてくれと渡されたという。どうやら今でも親交があるようだ。もし「GIVING LIFE」を訪れることがあれば、そのカツオノエボシについて尋ねてみると、オーナーが月に3万円のお小遣いをもらって修行していた時代の話をきかせてもらえるのではないかと思う。
(ヒゲの革職人のもとで修行していた時代に培ったカービングを施した時計)
二人目の師匠との出会い
オーナーにはもう一人師匠がいるそうだ。インスピレーションのままにカツオノエボシをつくる「ヒゲの革職人」が革細工を得意とする「アーティスト」だとすれば、二人目の師匠はまさに「職人」であり、そして「育ての親」のようなものだという。その師匠のことを語り始めるとあきからに語調がかわり言葉の節々にまで感謝で溢れているような印象を受けた。
一人目の師匠が突然工房を閉めることになり、横浜中華街に工房を構える「PLANET」を紹介してもらう。そこで出会ったのが二人目の師匠だ。「モノづくりにも人に対してもすごく丁寧で…職人としての姿勢や考え方、材料の仕入れ方など仕事のイロハを教えてくれた人」と惜しみない賛辞を贈る。
この師匠の下でならできるのではないかという信頼なのだろうか、「給料は低くてもいいので、お店の一角をください」そうお願いしたという。ここで学び、ブランドを立ち上げ、30歳までに自分のアトリエをもつことを決意したのだ。
「人間は一生のうちに逢うべき人には必ず逢える。しかも一瞬も早過ぎず一瞬も遅過ぎないときに」という言葉があるが、あながち楽観論ではないのかもしれない。ただおそらくこれは条件つきで、何か成し遂げようと決めたことを途中で投げ出した人には深く頷くことは難しいだろう。
平原を直進する竜巻のような熱情もさすがに消滅するのではないか?と思うほどに一つ目の工房の話をハラハラ聞かせてもらったが、そのまま回転力を失わず「PLANET」で尊敬できる職人と出会うことで、去年、山手駅前にアトリエをOPENさせるところまで漕ぎつけたのだ。
NPO法人たくみ21
最後に「なにかこれから作っていきたいものとかありますか?」と聞くと、片麻痺の方が片手でも使いやすい小銭入れをみせてくれた。マグネットが入っていて、小銭入れを固定した状態で片手でそれを開けて、楽に小銭を取りだせる。実はオーナーは福祉モノづくり集団「たくみ21」の理事もやっているそうだ。
「たくみ21」とは「自助具をはじめとする身近な福祉用具の創意工夫による開発と紹介を通じて、高齢者・障がい者の生活を応援する」モノづくりに取り組んでいるNPOだ。ただいいモノというのは福祉の枠を超えることがある。
たとえば見せてくれた小銭入れは片手が動かない人だけではなく、片手が塞がりやすい子育て中の人にも需要があるという。まさに「インクルーシブデザイン」である。
高齢者や障がい者に普遍的ニーズを発見するモノづくりは興味深い。たとえばZIPPOライターだって、戦争で片腕を失いマッチをすれなくなった人のために生まれた製品だというが、今ではそんなことは誰も気にせず広く使われている。
取材を終えて
レザーブランド「GIVING LIFE」は、ウェブサイトに載っている商品だけではなく、オーダーがあればメッセンジャーバックや花屋さん用のシザーケースもつくっていたりするようだ。今回取材させてもらったのも、海外で出会った本を日本語訳して本屋を通さずに出版している知り合いが「GIVING LIFE」にオリジナルのブックカバーや栞をオーダーしたことがきっかけだった。
ありあまる情報が手のひらに流れ込みながらも泡沫のように消えていってしまうこの時代。だからこそ、すこし仰々しく感じるかもしれないが、これだと思った書籍に革のカバーをかけることは「長くお付き合いをさせてください」と丁寧に向き合う真摯さの表れなのではないかと思う。
そして実際にアトリエ「GIVING LIFE」を訪れてオーナーに話を聞かせてもらうなかで確信した。革というのはきっと長い物語を綴る時間そのものなのだ。だからこそ物語の「はじまり」を大事にすることで、そこから流れていく関係はよりよい方向に彩られていく。もしそうなら「はじまり」にじっくりと時間をかけてもいい。
「誰かにプレゼントをするとき。その人のことを想いながら革や糸の色を選ぶ時間にこそ価値がある」。それは間違いないなと感じられた。そんなコンセプトでモノづくりをしているアトリエ「GIVING LIFE」は、これからもきっとかけがえのないGIFTを贈り続けてくれるのではないかと思う。